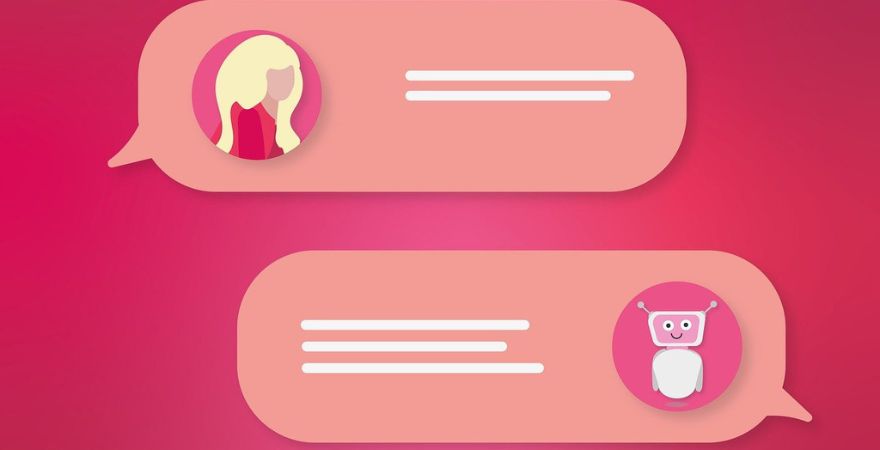
生成AIを利用して著作権法が問題となる3つのケースとは?
生成AIと著作権法との関係は?
ここ数年で生成AIの利用が一般的になり、特にChatGPTのようなチャットボットを利用したことがある方は多いのではないでしょうか。
その反面、生成AIを利用したことで、著作権法の問題が持ち上がるようになりました。しかし、どこからが著作権法に違反するか、判断が難しいかもしれません。
そこで今回は、生成AIと著作権法の関係などについて解説していきます。
生成AIとは、コンピュータが学習したデータを元に、新しいテキストや画像などを出力する技術です。近年になり、生成AIの技術開発が盛んに行われるようになりました。
しかし、生成AIを利用することで、著作権法に違反しないかどうかの問題が噴出したのです。
以下の場面で、著作権法の問題が発生するといわれます。
1.著作物を生成AIの学習用データに利用
2.著作物を生成AIの入力データに利用
3.生成AIの出力したテキストや画像を利用
この3つのケースごとに、著作権法との関係を見ていくことにしましょう。

ケース1・著作物を生成AIの学習用データとして利用する場合
たとえば、ある絵画の画像データを入力したら、入力した絵画とそっくりな画像が生成されたとしましょう。
その場合、生成された画像は元の絵画と似ているため、類似性は認められます。
そして、利用者が自ら絵画を入力データとして利用しているので、依拠性についても認められることになるのです。
よって、入力データと類似性があるデータを出力する生成AIを利用することは、リスクがあるといえるでしょう。つまり、著作権侵害の可能性があるといえます。

ケース2・著作物を生成AIの入力データとして利用する場合
たとえば、生成AIから出力されたテキストが、学習用データに用いられた著作物と酷似してほぼ同じように見えたとしましょう。
このケースでは、状況によって区別することが必要です。
まず、利用者が著作物の存在を知っていたときは、依拠性も認められると解されています。
ただし、利用者が知らなかったときの法的解釈が一定ではありません。依拠性が認められる(あるいは推定される)とする説と、認めるべきではないとする説に分かれているのです。

ケース3・生成AIの出力したテキストや画像を利用する場合
さらに、生成AIに利用されていない著作物で著作権侵害になるかというケースも考えなければいけません
たとえば、出力された画像が、生成AIとは関係のない既存の著作物と類似する場合です。
その場合には、利用者生成AIの力を使わず、自らの力でテキストや画像を作成した場合と同じになります。当該利用者が、元となった著作物の存在を知りながら生成AIを利用してその著作物と似たテキストや画像を生み出した場合に、依拠性が認められることになるのです。
今回は、生成AIと著作権法の関係などについて解説しました。
生成AIを利用して出力された生成物が他人の著作物と類似している場合、著作権法の問題が発生しやすくなります。
しかし、生成AIを利用すれば、事業などで大きな助けとなるはずです。著作権に注意しながら、生成AIを効果的に活用しましょう。
おすすめ記事
-
 人工知能の新たなフロンティア:会話型AIの実力と活用法
人工知能の新たなフロンティア:会話型AIの実力と活用法近年、会話型AIが多くのメディアやSNSで話題となっています。その人気は、多くの人々がこの新技術に興味を持ちつつ、一方でその利用にはまだ戸惑いを感じているという状況を反映しています。
-
 プロフェッショナルな自己紹介で人脈を拡大するテクニック
プロフェッショナルな自己紹介で人脈を拡大するテクニック新しい職場やプロジェクトが始まる際、最初のステップは自分を効果的に紹介することです。この瞬間が、あなたがどのような人物であるかを相手に示す重要な場面です。
-
 事業名選定の究極ガイド:成功への第一歩を踏み出すために
事業名選定の究極ガイド:成功への第一歩を踏み出すために事業をスタートする際、多くの人が何を名前として採用するかに頭を抱えます。ただの名前以上に、事業名はそのビジネスの顔とも言えます。


